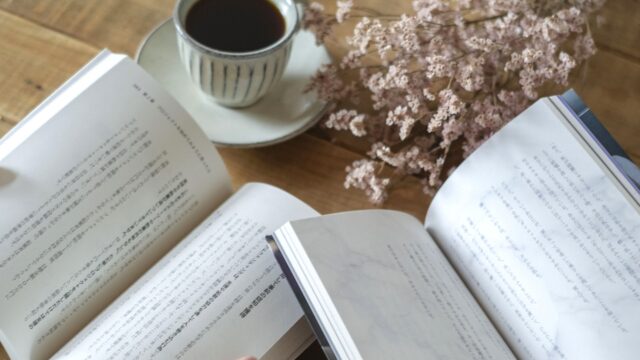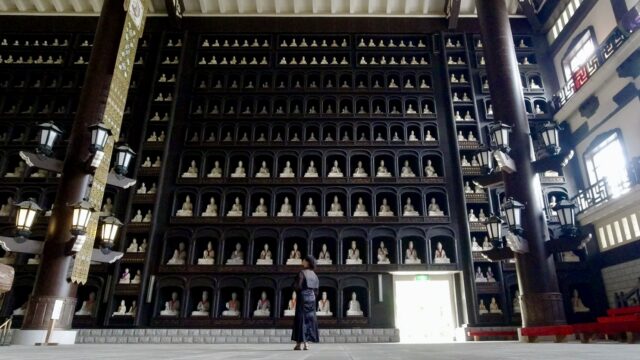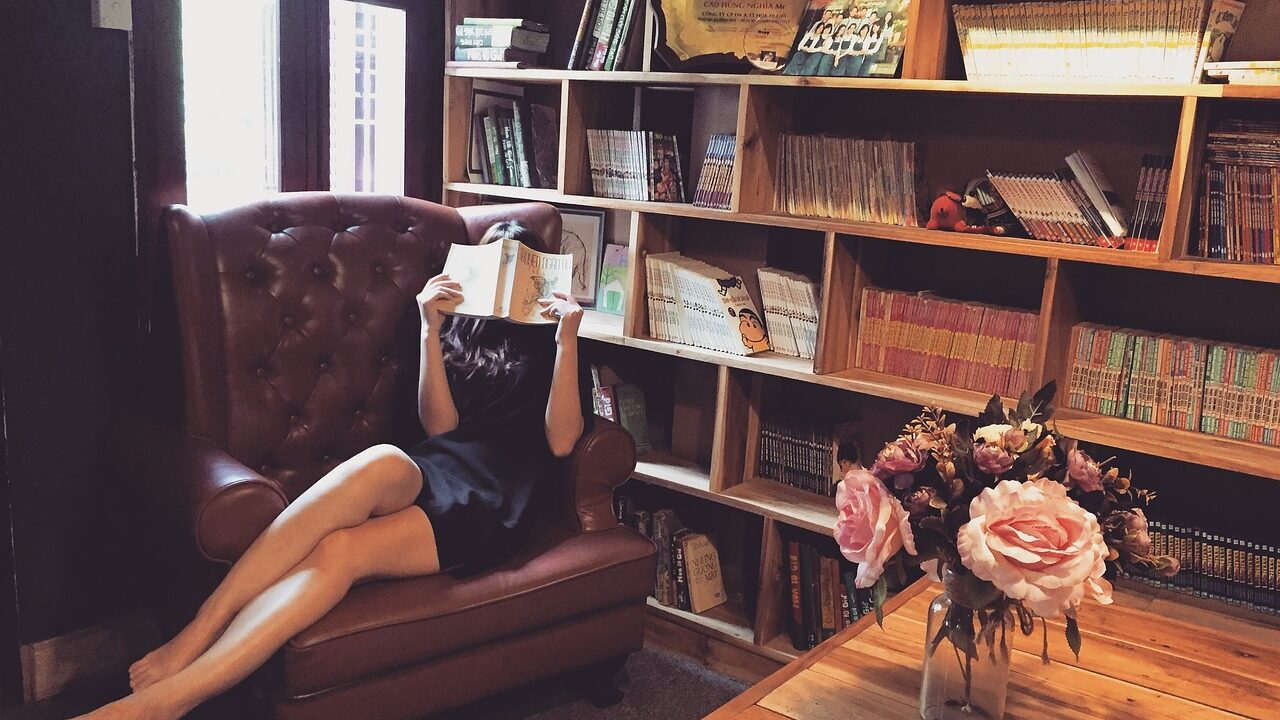発信頻度は私にとっての永遠の課題。
理由は明確で、何をするにしても「これって見てくれた人の役立つかな?」とか、「これを言ったらどうなるだろう?」と考えすぎてしまい、結果的に黙ることが多いからだ。
ブロガーの中でも絶対に下書き保存(しかも結構できているのに)が多い自覚はあるし、YouTubeの動画だって没にしたものは数知れず。
Xの下書きも果てしなくスクロールできる量がある。
考えて書き始めて、書きながらより考えて、公開する前に考えて、「人の目に触れる場所にだすのは辞めよう」と思ってしまうのだ。
とくに私は好きなものについて発信しているから、「公開するまで至らなくてもいいか」という気持ちが少なからずある。
そりゃあ公開した方が絶対にいいのだけれど、旅旅YouTubeは旅をしている時点で幸せだし、ブログやnoteも書いている時点で楽しい。それで、満足してしまう。
話を戻して、この「考えすぎ」が昔はすごく嫌だったのだけれど、30年も一緒にいる今は「大きな損をせずに済む」という点でとても助かると理解できるようになった。
だから、とてつもなくコンプレックスに思っていたり、今すぐどうにかしたいと考えていたりはしないのだけれど、不自由と言うか、発信の機会を逃している感覚はあって、「もうちょっと何かいい気持ちの置き所が見つかったらいいな」とはずっと思っている。
人間誰しも言いたいことを言えないのは身体に悪いし、
最中が楽しいのも幸せだけれど、世の中に出すと誰かに伝播して、予想もしなかった嬉しいことが起きる可能性があるから。
改めて考えるきっかけになった発信への憧れ

この件を改めて考えるきっかけになったのは、SNSで見かけた「漢字が難しすぎて読めない名前で情報発信してるやつの気が知れない」みたいな発言。
知り合いのリツイートで知ったのだが、その人は「自分も情報発信をする時に、どういう名前で発信するかはとても悩んで決めたので、ほぼ同意。ただし、本名なら仕方がない」という意見を添えていた。
早めに明言しておきたいのだけれど、私はこの発信に関して怒りは全くない。
むしろ「羨ましい」というか「憧れ」みたいな気持ちの方が強い。
この世の中には読めない漢字や造語、不思議な苗字なんてたくさんあるし、たった1つのアニメや小説で、それまでマイナーだった名前がメジャーに成り替わることもある。
しかも、名前なんてそうそう変えられない。
社名は創業者が決めていたり、本名は親が決めていたり、ライターネームもクライアントの意向があったり、本人の意思のみで決まるケースの方が少ないのではないだろうか。
でもたぶん、そんなに考えずに発信しているのだと思う。
これが!羨ましい!!!
きっと「漢字が難しすぎて読めない名前は辞めよう」論の人は、つまり「とにかく好きじゃない」ってだけで、個人の主観でしかないのだ。
巡り巡って私のこのnoteが届いたとしても、おそらくこの発信をしたことすら思い当たらないのではないだろう。
圧倒的に「自分しかいない発信」や、「個人の主観」を垣間見れるのは、創作物の魅力だと思う。
名前に関する考え方だけ見たら私とは相いないが、私も、そういう発信がしてみたい。
変な名前の私と、変わった名前の「逆旅出版」

先に主題を言ってしまったが、私の名前は「中馬さりの(ちゅうまんさりの)」と言う。
これはまあ、ほぼ本名だ。とくに苗字はそのまま。つまり、私は生まれてからずっと、中馬をやっている。
そして、私が運営しているのが逆旅出版(げきりょしゅっぱん)という出版社だ。
逆旅とは宿を意味する古語で、李白の詩にも出てくる。その詩は松尾芭蕉がオマージュしていて、そちらのバージョンも素敵だ。
先ほど、「自分も情報発信をする時に、どういう名前で発信するかはとても悩んで決めたので、ほぼ同意」とリツイートしていた知り合いは、この逆旅出版(げきりょしゅっぱん)のことを「ぎゃくたびしゅっぱん」と呼んでいて、シンプルに私に興味がないのだと思っている。
でも、それでいいのだ。
生きていて思うのだけれど、皆、政治がとにかく上手い。
私はあまり本音と建て前を察せないし、気の利いた言葉も思いつかない。
ぱっと見で読めない名前でいると、その辺りがとても便利だ。
初めましてと名のった後に、
- 浅学で申し訳ないと謝りながらルーツを聞いてくれる方
(自責で優しい方が多い) - 知らなかった!とルーツを聞いてくれる方
(健全な自己肯定感があり、コミュ力が高い) - 教養があり、パッと読める方
(同志にであった感覚になるし、趣味が合いがち) - 名前なんて記号なんだから、と「さりのさん」とか「御社は!」など読めない部分は回避して会話を続ける方
(エネルギッシュな方が多い) - 間違えた名前でそのまま呼び続ける方
(シンプルに興味がない) - 変な名前で迷惑だと怒る方
(睡眠とカルシウムが足りてない)
などなど、本当にその人の色が見える。
こんなことをしなくても、表情だとか声色で察せる方もいるだろうけれど、30年「パッと読めない名前」で生きている私にとっては手軽で便利な方法。
だから、この名前で10代の頃は散々いじられたけれど、フリーライターとして独立する時も苗字は本名のまま「中馬(ちゅうまん)」と名乗ることにした。
実際は鈴木や田中や小林がいいが、中馬以外での生き抜き方に不安もあった。
実際、逆旅出版も非常に便利だ。
上記のように相手のことを知れるのはもちろんだが、自社が大事にしたい思いやルーツを、物語として受け取ってもらいやすくなる。
逆旅出版とするだけで、
- 出版業を主軸にやっていきたい会社であること
- 古文や古語など過去の作品も大切にしていきたいこと
- 旅人にとっての宿のように、人生の道筋を決める拠点や分岐点が見つかる出版社でありたいこと
- お気に入りの宿のように何度もリピートしたくなる書籍を作りたいこと
などを、自然に語らせてもらえる。
ちなみに、出版業界には面白い名前の会社が多い。
株式会社ゲンロンとか平凡社(へいぼんしゃ)、而立書房(じりつしょぼう)、水声社(すいせいしゃ)、月曜社(げつようしゃ)、勁草書房(けいそうしょぼう)とか。
皆、字面からして綺麗だ。
逆旅出版はまず日本で、日本語を使った書籍を作っていくのだけれど、いつか海を越えて多言語で翻訳されることも夢見ていたから、漢字の美しさも取り入れたかった。
創業者としては、この手の話を「ビジョン」だとか「コンセプト」として語るべきなのだろうけど、如何せん察するのが苦手な私は、やっぱり「変わった名前ですね。どうして逆旅出版にしたんです?」なんて相手から話を振ってもらえるのは有難い。
こうやって、細かく考えて、なんとかなって今がある。
この考える工程を私は「思慮深さ」と読んでいて、行動が多少遅くなったとしても、自分らしさとして大切にしたい。
思慮深く、軽やかにいたい
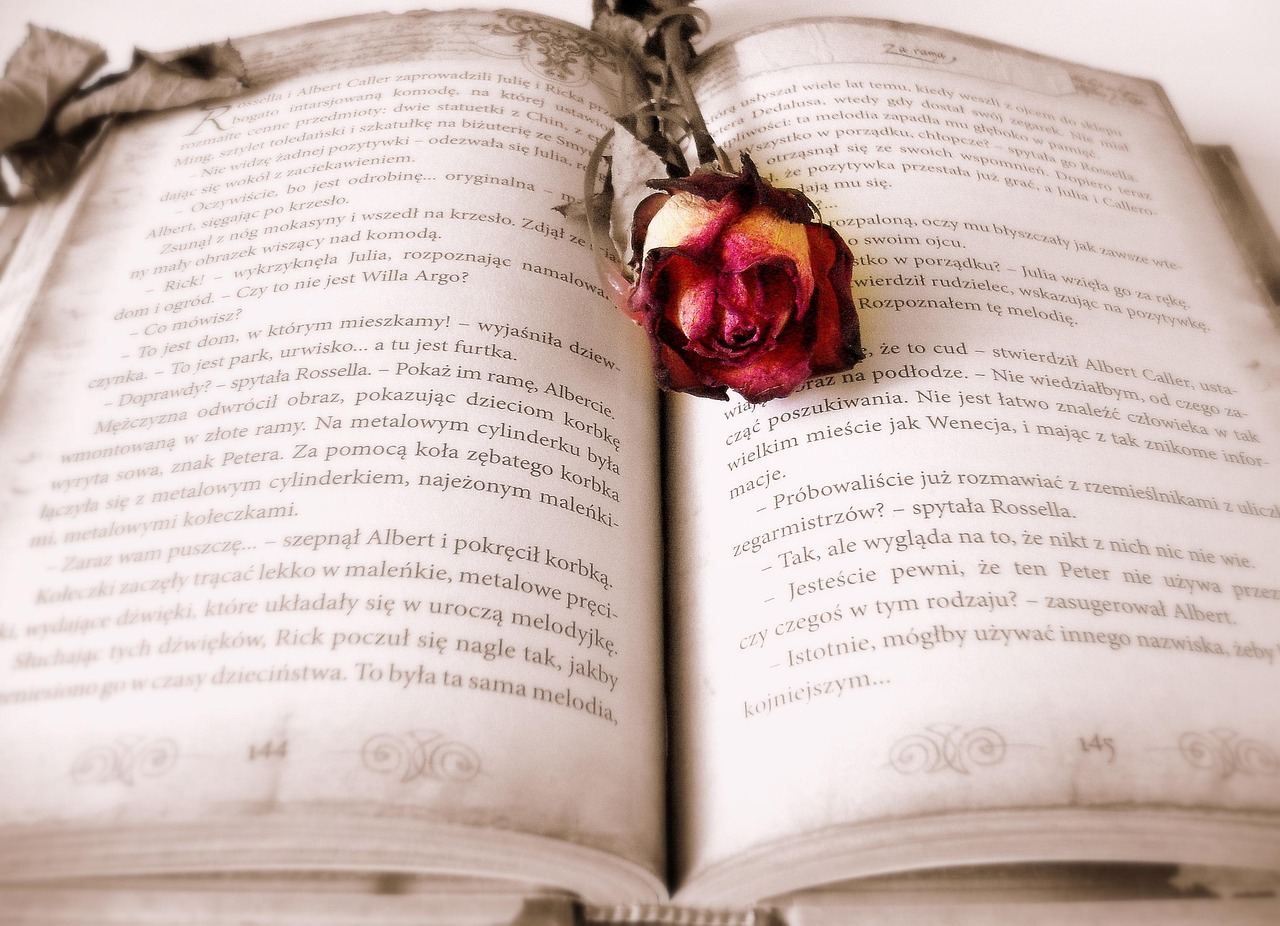
思慮深さが自分の良さだと思っている、でも、「自分しかいない発信」や「個人の主観」が垣間見える軽やかさに憧れがある。思ったことをポンと発信できる身軽さ。
この矛盾した気持ちを整理していくと、「思慮深く、軽やかにいたい」という言葉に辿り着いた。つまり、個性としてしっかり考えた上で、気軽に発信したいのだ。貪欲。
最初にも語ったが、発信する時に私は「見てくれた人の役に立つかな?」とか「嫌な気持ちにならないかな」なんて考えている。
その考えることは息を吸うようなもので、とくに意味はないし、単純にひとりでも多くの人の役に立てば嬉しい程度のこと。
でも「漢字が難しすぎて読めない名前は辞めるべきか否か」というたった1つの要素でさえ、平行線だ。
私がいくら言葉にこめた思いを語っても通じない相手には通じない。
私自身だって、異なる考えを「面白いな」とか、発信の姿勢は「興味深いな」と思うことはあっても、変わった名付けを私は辞めないし、改名の予定もない。
今後も「中馬」を面白がってくれて、「逆旅出版」の理由を知りたいと言ってくれる人達が好きなまま。
「分かる人」に向けて発信すればいい。中馬が読めて、逆旅出版の意図が分かる人。私の思慮深さを面白がってくれる人。そういう人たちに向けて、思慮深く、軽やかに発信していこう。
そう考えると、あの果てしなくスクロールできる下書きの山も、実は宝の山なのかもしれない。
ひとり旅をテーマにVlogやホテルのレビューなど情報をシェアしています。
よかったらこちらも見てもらえると嬉しいです